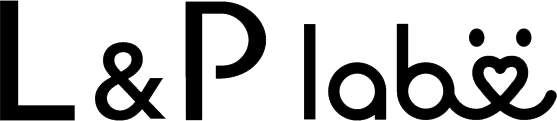
【首輪職人監修】犬の首輪サイズ測り方ガイド|首回りの測り方で失敗しない選び方

首輪のサイズ選びに悩んでいませんか?愛犬の首輪がきつすぎると苦しそうだし、ゆるすぎると散歩中にスポッと抜けてしまうかもしれません。「犬の首輪サイズ測り方ガイド」では、正しい首回りの測り方と失敗しないサイズの選び方をわかりやすく解説します。大切な愛犬の安全と快適のために、首輪サイズのポイントをしっかり押さえておきましょう。
首輪サイズ選びが重要な理由
愛犬に合った首輪サイズを選ぶことは、安全面でも快適さの面でも非常に重要です。首輪がきつすぎると、犬の首や喉に負担がかかり、最悪の場合呼吸困難や皮膚炎などのトラブルにつながる恐れがあります。一方で、首輪がゆるすぎると散歩中に首輪が外れて犬が逃げてしまったり、思わぬ事故の原因にもなりかねません。実際、適切なサイズの首輪を選ぶことは愛犬の命と安全を守ることにつながるのです。
また、犬それぞれ首回りの太さや毛量は異なります。同じ犬種でも個体差があるため、「○○犬だからこのサイズで大丈夫」と決めつけるのは危険です。成長途中の子犬であれば尚更、数ヶ月で首回りのサイズがどんどん変化しますし、成犬でも季節による被毛の増減や体重変化で首回りサイズは変わることがあります。愛犬にジャストフィットする首輪を選ぶには、まず正確に首回りを測定することが欠かせません。
愛犬の首回りの正しい測り方
首輪サイズで失敗しないためには、愛犬の首回り(ネックサイズ)を正しく測ることが第一歩です。ここでは首回り寸法の測定手順と、測定時に押さえておきたいポイントを解説します。
犬の首輪サイズ測り方 4ステップ
愛犬の首回りを測る際は、次の手順で行いましょう。
正確なサイズを測るため、犬がリラックスしてまっすぐ立つか、おすわりした姿勢で測定します。伏せたり寝転んだ状態では正しい寸法が測れないので注意してください
メジャー(柔らかい巻き尺)を当てる位置は首の付け根(耳のすぐ下)から指2本分ほど下がった箇所です。耳に近い細い部分で測ることで、首の一番太い部分だけ測ってしまうよりも、首輪がスポッと抜けにくい適切な位置を計測できます。この位置が実際に首輪を装着する位置に相当します。
メジャーを首に巻きつけ、できるだけ毛をかき分けて地肌に沿わせるように測定します。毛量が多いワンちゃんや毛質がふわふわのワンちゃんは、毛の上から測ると実際より大きめのサイズになりがちです。正確に測るために、被毛を押さえて首周りの実寸を測りましょう。メジャーが無い場合は紐やリボンを首に巻きつけて長さを測ってもOKです。
とえば首回り実寸が29cmであれば、首輪サイズは30~31cm程度が目安です。この1~2cmの余裕分が、実際に首輪を装着した際に指がスッと1~2本入るゆとりに相当します。首輪と首の間に指が2本入るくらいのスペースがあれば、きつすぎず緩すぎない「優しいフィット感」になります。逆に指が一本も入らないようでは締め付けすぎですし、あまりに余裕がありすぎると簡単に抜けてしまうので注意しましょう。
測定時のポイントと注意点
上記の手順に沿って測れば、愛犬の首回りサイズをほぼ正確に把握できます。さらに測定時に覚えておきたいポイントや注意点をまとめます。
嫌がる場合は無理せず慣らす
初めて首回りを測るとき、犬が嫌がる場合があります。おやつを見せて気を逸らしたり、誰かに協力してもらい優しく声かけしながら行いましょう。どうしても難しい場合は無理に測ろうとせず、時間をおいて再チャレンジします。

子犬はこまめに測り直す
成長期の子犬は数週間で首回りが大きくなります。子犬用の首輪を選ぶ際も、まず測定してサイズを把握することは大切ですが、そのサイズはすぐに変わる前提で考えましょう。子犬の場合は成長に合わせて1~2ヶ月ごとに首回りを測り直し、適切なサイズに買い替える or 調整するようにします。最初は少し余裕のあるサイズを選び、成長してフィットしてきたら新しい首輪に移行すると良いでしょう。
測定結果はメモしておく
測った首回り寸法は忘れないようにメモしておきます。首輪を購入するときにその数字を元に選べば失敗が少なくなります。
複数の犬を飼っている場合、それぞれ首回りサイズが違うので間違えないよう記録しましょう。
測定結果をもとにした首輪サイズの選び方
首回りの実寸(+ゆとり分)という愛犬にとっての適正サイズがわかったら、その数値を基準に首輪そのものを選んでいきます。首輪選びではサイズ表記の見方や調整方法にも注意が必要です。ここでは測定結果を活かして首輪サイズを選ぶ際のポイントを解説します。
製品のサイズ表記を確認する
首輪の製品ごとに「S・M・L」などサイズ区分や、適応首回り◯cm~◯cmといった表示があります。必ず商品の詳細サイズ(首回り◯~◯cmなどの表記)を確認し、愛犬の首回りがその範囲内に収まっているものを選びましょう。理想的には、愛犬の首回り+ゆとりの長さが、首輪の調整可能レンジの中間あたりにくるサイズだとベストです。例えば首回りゆとり込みが30cmなら、「首回り27~33cm対応」のような首輪だと余裕を持って調節できます。ギリギリより余裕のあるサイズを選ぶのがコツです。
号数や犬種目安に頼りすぎない
商品によっては「○号」や「○kgの小型犬向け」などの表記もありますが、犬種や体重だけで判断せずあくまで実測した首回りサイズを基準にします。「同じ犬種だからうちの子もMで大丈夫だろう」「今使っている他社製のSだから今回もSでいいはず」という判断は避けましょう。実際、それで失敗してサイズ交換になるケースも多いといいます。首輪はメーカーやデザインによって寸法が微妙に異なるため、必ず自分の愛犬の首回りを測ってから購入する癖をつけましょう。

現在使用中の首輪から測る方法も
もし今つけている首輪があり、フィット感がちょうど良いなら、その首輪の長さを測って参考にする方法もあります。バックル式の首輪であれば、穴に通して留めている位置の穴から留め具までの長さを測ると実際の装着時サイズがわかります。ワンタッチ式(バックルでカチッと留めるプラスチック製など)の場合は、留め具の端から端までをまっすぐ伸ばして測りましょう。このように今の首輪の寸法を把握しておくと、新しい首輪選びの際に比較検討しやすくなります。
サイズ選びでよくある失敗と対策
首輪のサイズ選びでありがちな失敗例と、その対策をいくつか紹介します。
- 失敗例① イメージや勘に頼って購入
実測せずに「何となくこのくらいだろう」とサイズを決めてしまうケースです。プレゼント用にサイズが分からず勘で選んだり、体重や見た目の印象だけで選ぶのもNGです。対策: 必ず首回りを測定し、その数値を根拠にサイズを選びましょう。プレゼントの場合でも相手に協力してもらい首周りを測ってもらうのが確実です。 - 失敗例② 他の犬や製品のサイズを流用
「同じ犬種の○○ちゃんがMサイズだからうちの子もMだろう」「今使っているブランドXの首輪がSだから今回もSで平気」といった思い込みも失敗のもとです。犬は同じ犬種でも個体差がありますし、メーカーごとにサイズ基準も異なります。対策: 他の犬や他製品のサイズは参考程度にとどめ、自分の愛犬の首回り実測値を最優先してください。製品ごとのサイズ表を確認し、少しでも合わない可能性があればワンサイズ上げるか下げるか検討しましょう。 - 失敗例③ 成長や季節変化を考慮しなかった
子犬の成長によるサイズ変化や、毛が伸びたり冬毛でボリュームアップする季節変動を考えずピッタリサイズを選んでしまう場合です。あとできつくなって買い直すことになります。対策: 子犬の場合は成長分を見越して調節範囲が広めの首輪を選ぶ、成犬でも毛量が増える冬場は少しゆるめに調節するなど、将来の変化も織り込んでサイズを選択・調整しましょう。定期的に愛犬の首回りを測り直し、現在のサイズが適正か確認する習慣をつけるのも大切です。
首輪装着後のフィットチェック方法
選んだ首輪が実際に愛犬にフィットしているか、装着後にも必ずチェックしましょう。以下の方法で適切なサイズかどうかを確認できます。
指を入れてみる
首輪を装着したら、首と首輪の間に指を差し込んでみます。人差し指と中指の2本が無理なく入る程度のゆとりがあれば理想的なフィット感です。指が1本も入らないようであれば明らかにきつすぎるため、すぐに調整(穴を変える、別のサイズに交換する等)が必要です。逆に指が3本4本と入ってしまうほど余裕がある場合は緩すぎますので、こちらも調節しましょう。
引っ張って抜けないか確認
次に、首輪が抜けてしまわないかテストします。首輪をつけた状態で、首輪自体を耳のすぐ下あたりまで動かし、後頭部方向(犬の頭の方)へ引っ張ってみましょう。このときスポッと首輪が頭から抜けてしまうようならサイズが大きすぎます。実際、犬が後ずさりするときに首輪がすっぽ抜けてしまう事故も起こり得ます。引っ張っても抜けないことを確認できれば、まず安心です。
様子を観察する
散歩中や普段首輪をつけているときの愛犬の様子もチェックしましょう。首輪の跡が首にくっきりついていたり、毛がすり切れているようならきつすぎるサインです。逆に首輪がくるくる回ってしまうほどゆるい場合もフィットしていません。適切なサイズの首輪は、犬の動きに追従しつつも簡単には抜けず、犬も嫌がらずに快適そうにしています。装着後しばらく様子を見て問題がないか確認することが大切です。

「実は私も、愛犬の首輪サイズ選びで失敗した経験があります。以前、愛犬にオシャレな革の首輪をネットで購入したのですが、サイズをしっかり測らずに選んでしまい、届いた首輪が少しきつめでした。幸いすぐ交換してもらえましたが、愛犬に窮屈な思いをさせて反省しました。それ以来、首輪を買う前には必ず首回りを測り直し、指が2本入る余裕があるか確認するようにしています。皆さんも愛犬にベストなサイズの首輪を選んで、快適で安全なお散歩を楽しんでくださいね。」
犬の首輪サイズに関するQ&A
- 首輪と首の間には指何本分の余裕を持たせるべきですか?
-
一般的には指がスッと2本入る程度の余裕を持たせるのが良いとされています。これは約1~2cmほどの隙間に相当し、きつすぎず緩すぎないフィット感の目安になります。ただし、小型犬など首回りが細い犬では指1本ぶんでも十分な場合があります。いずれにせよ、首輪装着後に指を差し込んでみて窮屈でないことを確認しましょう。
- 測ったサイズがちょうど境目の場合、首輪は大きめと小さめどちらを選ぶべき?
-
基本は大きめサイズを選び、調節してフィットさせるほうが安全です。小さすぎる首輪は物理的に装着できなかったり、無理につけても犬が苦しくなります。大きめであれば余分な長さを調整穴で締めたり、余ったベルト部分をカットすることもできます。特に成長期の子犬の場合は、少し余裕があるぐらいのサイズを選んでおいた方が長く使えます。
- 首輪の幅(太さ)は首周りサイズ選びに関係ありますか?
-
首輪の「長さ(首回りサイズ)」とは直接関係ありませんが、幅の選択も犬の快適さに影響するため覚えておきましょう。一般的に、小型犬には幅1cm前後の細めの首輪、力の強い大型犬には2~3cm程度の幅広の首輪が適しています。首輪幅が広いと首への荷重が分散されますが、重く硬くなる傾向があります。逆に細すぎる首輪は食い込みやすいので、犬種や首周りの太さに応じてバランスの良い幅を選ぶと良いでしょう。
- 長毛種の場合、毛の上から測っても大丈夫?
-
正確なサイズを知るために、長毛の犬は毛をかき分けて地肌を測るようにしましょう。毛のボリュームがあるときは、その分首輪も緩くなりがちです。地肌で測った上で1~2cmのゆとりを足せば、毛を含めても窮屈すぎないサイズになります。逆に冬場など毛量が増えて首輪がきつく感じる場合は、無理をせず一段階大きいサイズに買い替えるかハーネスなども検討してみてください。
- 子犬の首輪はいつからつけるべき?サイズ選びの注意点は?
-
一般的に生後2~3ヶ月頃には首輪に慣れさせ始めると良いと言われます(※首輪デビューの時期については別記事「子犬の首輪はいつから?」で詳しく解説)。サイズ選びでは、子犬用だからといって特別な測り方はありませんが、成長速度が速いのでこまめなチェックが必要です。最初は調節範囲に余裕のある軽い素材の首輪を選び、嫌がらず装着できるよう慣らしていきましょう。成長に伴ってサイズが合わなくなったら、その都度買い替えることも視野に入れてください。
コメント